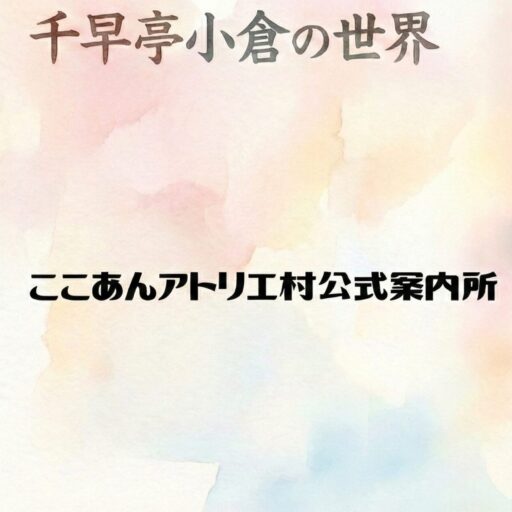これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
今日のロマコメ号は、移動式の折り紙動物園だった。返却された本よりも、子どもたちが置いていった紙の創造物のほうが多いのではないか。書架の隙間に挟まれたエビ。カウンターの隅に置かれたラッコ。請求記号もISBNもない、まったくもって分類不能なオブジェクトたち。秩序を生命線とする司書への挑戦としか思えない。
(前の私なら、もっと素直に喜べたのに…)
輪の中心にいたのは、小学2年生くらいの少年だった。彼の指先から、まるで魔法のように生命が生まれていく。あっという間に仕上がっていく動物たち。それはそれで、完結したひとつの秩序だった。一枚の正方形が、定められた手順で二次元の形態へ、時には三次元の形態へも変容する。
美しい。潔い。私の好きな世界だ。
けれど、私の手に握らされた折り紙は、それとは違っていた。女の子がくれた、少し歪んだハート。「ちなつせんせい だいすき」という、覚束ない文字が書かれている。彼女の手の熱が、まだ残っているような気がした。これは、秩序ではない。感情の、生の塊だ。どう処理すればいい? 書架のどこにも、この感情の置き場所はない。
折り紙少年が、ふと、「お化けの折り紙もあったんだけど」とつぶやいた。
「忘れちゃったんだ」
その言葉に、小川洋子さんの『博士の愛した数式』が頭をよぎった。記憶が80分しか保たない博士。先生にとって、世界は常に新しい数式で満たされていた。忘れることと喪失とはちがうもの。だとすれば、博士が愛した数式の美しさが永遠だったように、少年が忘れた「お化け」も、彼の中で美しい記憶として残るかもしれない。
それとも――。
忘れたいのに、忘れられない記憶もある。
「お化け」という言葉の響きが、不意にあの日の瓦礫の山を思い出させる。形を失い、分類不能になったモノたちの、静かな叫び。日常という秩序が、巨大な無秩序に飲み込まれた、あの日の手触り。
私は、子どもたちとのただのやりとりに、何を重ねているのだろう。ここあん図書館の運行マニュアルには、「心に寄り添う」とある。「『大変でしたね』といった安易な同情は避ける」とも。私はただ、聞くことに徹するだけだ。少年の「忘れちゃった」という言葉を、そのまま受け取る。分類も解釈もせず、ただ事実として記録するのだ。
業務終了後、車内の清掃をしながら、散らばった折り紙たちを集めた。本来なら廃棄すべきものだろう。しかし、どうしてもできなかった。真木先輩なら、きっと微笑んで「宝物ですね」と言うだろう。美桜さんなら、いつの間にか自分の机のガラクタの山に混ぜてしまうに違いない。そして高島副館長は、「業務に関係のないものは速やかに処分するように」と眉をひそめるだろう。
結局、ラッコとエビは業務日誌に挟み込んだ。そして、あのハートは、誰にも見られないよう、そっと自分の手帳のポケットに滑り込ませた。分類不能。処理未了。私の内なる書棚の秩序が乱れてしまうけれど。
……閉架書庫の鍵が、やけに重く感じられた。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)