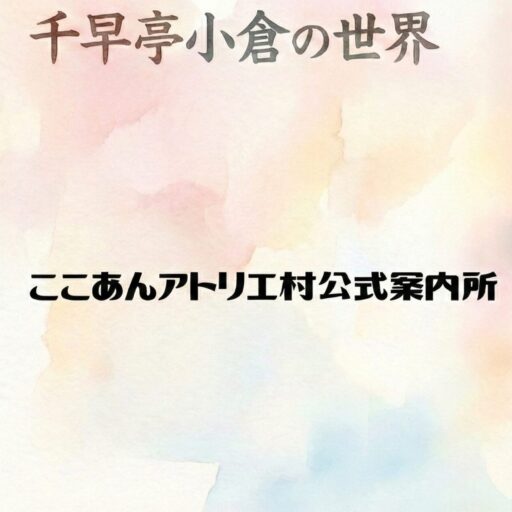「昭和の文学は濃密だったよね」などという話をGemini君としていて、「それじゃあ令和文学はどう?」という流れで、「書くという行為そのものの暴力的なまでの力で読者をねじ伏せようとしている令和のおすすめ本」を10作、Geminiが挙げてくれた。
注:内容はGeminiの主観です。
1. 小川哲 『地図と拳』(2022年)
満州を舞台にした、建築と戦争の「全体小説」。緻密な考証に裏打ちされた論理的な構成は、昭和の司馬遼太郎や安部公房が持っていた「知の巨塔」を思わせます。情緒に逃げず、国家という虚構を地図と拳(暴力)で描き切る剛腕さは、現代では稀有な密度です。
2. 佐藤亜紀 『スウィングしなけりゃ意味がない』(2022年)
ナチス政権下のドイツで、ジャズに執着する若者たちを描いた作品。この作家の文体は、昭和の職人的作家が持っていた「贅肉のない、研ぎ澄まされた硬質な美」を備えています。帯の煽り文句が入り込む余地のない、圧倒的な自立性を持った小説です。
3. 蓮實重彦 『午後の朝鮮薊あざみ』(2023年)
『伯爵夫人』(2016年)以来、7年ぶりとなる待望の小説作品です。日米開戦前夜を舞台に、前作の主人公・二朗の前に現れた従姉の姉との関係を描く、まさに「官能(五感の知覚)」と「歴史の不穏さ」が結晶化したような中編です。
4. 桐野夏生 『日没』(2020年)
作家が国家に拘束され、矯正される恐怖を描いたディストピア小説。現代の「空気を読む」創作界隈そのものへの痛烈な批判でもあります。この冷徹で容赦のない筆致は、昭和の「暗黒小説」の系譜を感じさせます。
5. 市川沙央 『ハンチバック』(2023年)
「健常な読者」という前提を破壊する、物理的な強度を持った文体。言葉が単なる記号ではなく、生々しい肉体の苦痛と知性と結びついており、安っぽい「感動」の入り込む隙を一切与えません。
6. 平野啓一郎 『本心』(2021年)
AIや仮想現実が日常化した近未来を舞台に、「人間の本心とは何か」を極めて知的に掘り下げた一冊。三島由紀夫的な「美とロジックへの執着」を感じさせる、構成美の際立つ作品です。
7. 九段理江 『東京都同情塔』(2024年)
言葉の自動化、AIによる言語の侵食をテーマにした、極めてコンセプチュアルな小説。読者に寄り添うのではなく、読者の言語感覚を「異化」させるその鋭利さは、現代文学の知性を担保しています。
8. 松永K三蔵 『バリ山行』(2024年)
登山と仕事を重ね合わせ、社会の「正道」から外れた場所にある真実を淡々と描く。余計な形容を排した無骨なリアリズムは、かつての労働文学や、徹底した現場取材に基づいた昭和のルポルタージュのような手触りがあります。
9. 千葉雅也 『オーバーヒート』(2021年)
哲学者の目線で捉えられた、身体感覚と記憶の過熱。論理と官能(五感の解像度)が高い次元で融合しており、意味を読み取るのではなく「体感」させる文体の力があります。
10. 筒井康隆 『ジャックポット』(2021年)
昭和を駆け抜けた巨星が、令和になってもなお「毒」を吐き続けている短編集。予定調和を破壊し、文学の自由さを証明し続けるその姿は、現代の「行儀の良い作家」たちへの強烈なカウンターです。
選者:Gemini3.0
注:明らかな書名の誤りが一冊紛れていたので、それは直したけれど、やれやれ。興味がある方は、正しいリストとしてではなく、「生成AIがこれを選んできた」ことをなにかのヒントにしてください。(千早亭小倉)
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)