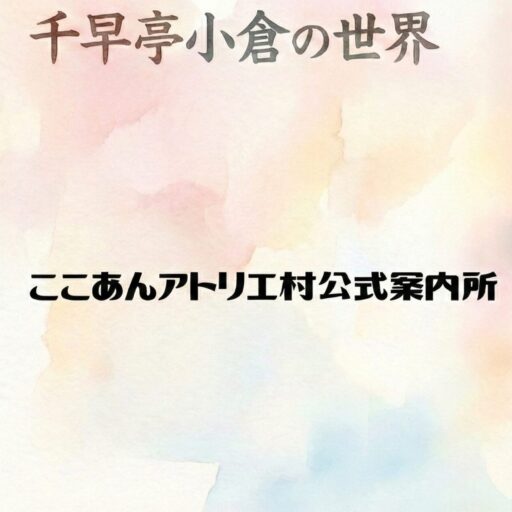これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
今日の巡回先は、大学の跡地が湖になった、そのほとりに建てられた仮設団地。ロマコメ号をいつもの場所に停め、本のコンテナを並べていく。背表紙の高さ、NDC分類の若い順。完璧な直線と秩序。それが私の防衛線であり、この混沌とした世界における、ささやかな抵抗だ。
午後の日差しが日よけテントの影をくっきりと地面に落とす頃、それは起こった。
「あら、まあ……萩原さんじゃないかい!?」
甲高い声に、私の肩がぴくりと跳ねる。声の主は、隣の仮設団地から歩いてきたという、小柄なおばあちゃん。彼女の視線の先には、ちょうど私が貸し出し手続きをしていた、萩原さんの後ろ姿があった。
萩原さんは、ゆっくりと振り返ると、目を丸くして、持っていた本を取り落としそうになった。
「……鈴木さん? あんた、生きておったのかい! ああ、こんなとこにおったの!」
次の瞬間、私の小さな秩序の聖域は、感情の奔流に飲み込まれた。二人は駆け寄り、しわくちゃの手を取り合って、泣きながら、笑っていた。「あのこと」の後、避難所で別れて以来、ずっと互いの安否も知れなかったのだという。
私の頭は、この出来事をどう分類すべきか、高速で回転を始める。『事象:利用者間の再会』『特記:「あのこと」による離散後の初確認』。しかし、そんな無機質な文字列では、目の前の光景の熱量を、一ミリも記録することなんてできない。
二人の周りだけ、空気があたたかく形が違って見えた。私の完璧に整列した本棚も、彼女たちの前ではただの背景に成り下がる。ここは図書館。静粛に。そう喉まで出かかった自分に、昔の私が冷ややかに囁く。
(本気で言ってるの? この光景を見て、最初に思うことがそれ?)
違う。そうじゃない。
ふと、ケイト・ディカミロの『エドワード・テュレインの奇跡の旅』を思い出した。持ち主の少女と離れ離れになり、海の底に沈み、ゴミの山に捨てられ、様々な人の手を渡り歩く、陶器のうさぎの物語。エドワードは、自分では動けない。ただ、そこに「在る」ことしかできない。でも、彼の存在が、偶然と奇跡を引き寄せ、人の心と心を繋いでいく。
このロマコメ号も、エドワードと同じなのかもしれない。
私がやっていることは、本という「物」を、定められた場所から場所へ運ぶだけの、単調な作業だと思っていた。けれど、この車が、この本の並んだ空間が、ただそこに「在る」ことで、離れ離れになった人々が再び出会うための、小さな座標軸になっている。私が守りたかった秩序は、本の背表紙が作る直線なんかじゃなくて、こういう、目には見えないけれど、確かに生まれる人と人との繋がりという名の、新しい秩序だったのかもしれない。
貸出記録には残らない、今日の出来事。でも、私の心の書棚の、一番大切な場所に、そっと差し込んでおこう。分類は、まだ、できないままで。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)