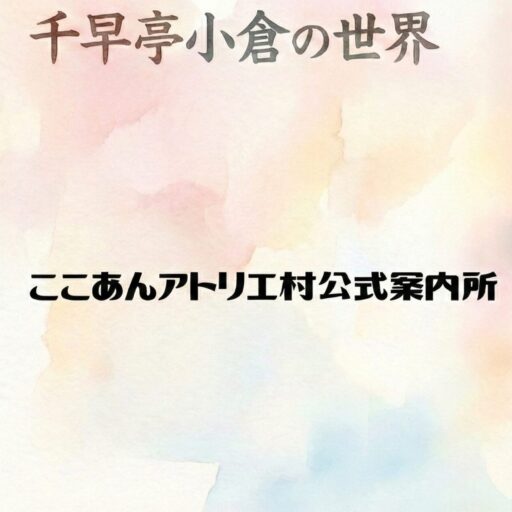これは日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
「活動日誌への記載事項:本日午前、ボストー区の復興住宅前における滞在時間62分。利用者3名。貸出冊数5冊」
数字だけを見れば、この活動(移動図書館車による訪問)は非効率極まりない。厳守すべき「秩序ある運営」からはかけ離れている。以前の私なら、この空白の多い時間に苛立ち、改善策のリストを頭の中で作成していただろう。
けれど、ロマコメ号のステップを上がってきた、同世代の女性――。子供向けの絵本を探しながら、話はいつの間にか、好きなアイドルの話へと。
「この衣装、見てくださいよ! 先月のライブのなんですけど、これをフェルトで再現して、うちの子のぬいぐるみに着せてあげたら、すっごく喜んで」
彼女が語るのは、テレビの中の流行や、刹那的な熱狂。私の脳はそれを自動的に分類しようとする。だが、自分の手で何かを生み出した喜びを語る彼女の、少し誇らしげな横顔は、どの分類コードにも収まらなかった。
この日、彼女と入れ替わるようにやってきたのは、杖をついた80代のおばあちゃんだった。
「駅長さんだったのさ、うちの人はさ」
借りる本を決めかねている彼女の、ぽつりとした呟きから、物語は始まった。昔、夫が勤めていた小さな駅では、事務所の古い柱時計が何とも言えない良い音で鳴ったこと。
「ネジを巻くのは、主人の仕事だったのさ。毎朝同じ時間にね。時計がボーンって鳴るでしょう。その音を聞くと、ああ、今日も一日が動いてるなって、安心したものさ」
駅舎が取り壊され、時計もどこかへ行ってしまったこと。もう二度と聞けない、けれど耳の奥にだけはっきりと残っている時を告げる音。
私は、ただの聞き手になっていた。彼女の言葉は、どの書棚にも収められていない、たった一人の歴史。検索しても決して出てこない、生きた時間の記憶そのものだ。
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチは、歴史からこぼれ落ちた名もなき女性たちの「声」を集め、『戦争は女の顔をしていない』を編んだ。私もまた、そのような「声」を聞いているのではないか。ロマコメ号は本を運ぶだけの車じゃない。失われ、忘れ去られようとしている物語を、そっと掬い上げるための場所になっている。
ロマコメ号の貸出受付は、バーコードリーダーではなく、手書きのノートだ。
この前時代的なシステムは、たしかに、早急に改善すべき「エラー」かもしれない。けれど、おばあちゃんの名前と、借りていく本のタイトルを一文字ずつボールペンで書き込む、その数十秒。沈黙とインクが紙に染みていく時間があるからこそ、彼女は言葉を紡ぎ始めるのかもしれない。貸し出しノートは、単なる記録簿ではない。誰が、いつ、どんな物語を求め、そしてどんな物語を私に託してくれたのかを記す、ロマコメ号の滞在中にだけ開かれる歴史書だ。
利用者数という「量的データ」は、この活動の本質を何も語ってはくれない。数字や効率だけが秩序ではない。人と人が向き合い、物語が生まれる、不確かで温かい時間。それが、この場所を守るための、新しい秩序に……なんて、らしくない感傷だ。活動日誌には、もっと事務的に書かなければ。私は冷静さを取り繕い、日誌の「定性的記録」の欄に、おばあちゃんとの会話の要点だけを淡々と記した。けれど、ノートの隅に、私にしかわからない記号で、こう書き加えることは忘れなかった。
――柱時計の、音。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)