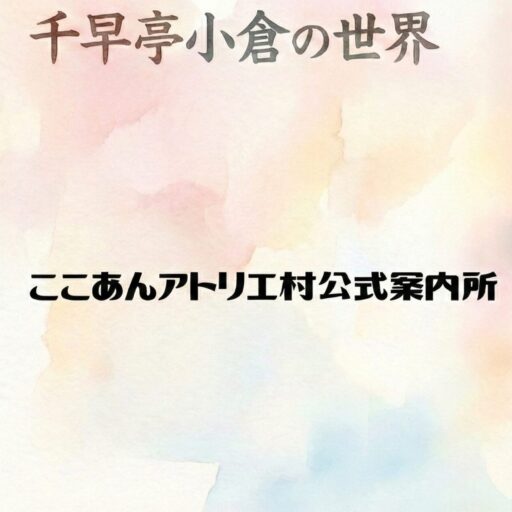これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
昨夜、ロマコメ号で運行先のボストー区から図書館に戻る途中のこと。それは、災害で生まれたあの大きな湖の縁をなぞるように走る、灯りの少ない道だった。予定通りの時刻、完璧な運行計画。私の思考は、返却された本の分類と、明日の巡回ルートの最適化で満たされていた。
その時だ。ヘッドライトが照らす闇の中から、突然、小さな影が飛び出してきた。
咄嗟にブレーキを踏む。タイヤがアスファルトを掴む短い悲鳴。車体が軽く前のめりに沈み、書架の本がカタカタと不穏な音を立てた。心臓が、喉のすぐ下までせり上がってくる。あの日の揺れとは違う。でも、予期せぬ出来事が日常に亀裂を入れる、あの感覚は、同じだ。
影の正体は、カルガモの親子だった。親鳥を先頭に、五、六羽の雛が、まるで何事もなかったかのように、短い脚で懸命にアスファルトを横断していく。私の完璧な運行計画(ダイヤ)を乱したことなど気にも留めず、一列になって、そそくさと闇に消えていった。
呆然とハンドルを握りしめる。私の管理する世界の外側には、常にこういう予測不能なものが存在している。交通規則という名の秩序など、彼らの生存本能の前では意味をなさない。
不意に、アーノルド・ローベルの絵本『ふたりは ともだち』の世界が頭をよぎった。もし、かえるくんが運転していて、がまくんが隣に座っていたら、この光景をどう見るだろう。「なんて のんきな おきゃくさんだろう!」なんて言って、二人で笑い合ったのかもしれない。あの世界では、あらゆる闖入者は、物語を豊かにする要素として受け入れられる。
……昔の私なら、「可愛い」なんて、声に出して笑ってしまえたかも。今、この胸を占めるのは、安堵よりも、私の制御できない無秩序に対する、冷たい恐怖だ。
図書館に戻り、閉架書庫で最後の点検をしていた時、第二の侵入者は現れた。大雨のせいか、コンクリートの床がじっとりと湿っている。その隅に、見たこともない虫がいた。金属光沢のある、奇妙な形の甲虫。NDC(日本十進分類法)のどこを探しても、分類コードが見つからないような、異質な存在。
一瞬、殺虫剤を探そうと体が動く。秩序を乱すものは、速やかに排除しなければならない。でも、同時に、もう一人の私がささやくのだ。「昆虫図鑑、486の棚へ。まずは同定を試みること」と。この、忌々しいまでの司書の性。
結局、私はその虫をちりとりに乗せ、外の植え込みにそっと逃がした。駆除でもなく、観察でもない、実に中途半端な着地点。
ここあん村で暮らすということは、こういうことなのかもしれない。カルガモの親子も、名も知らぬ虫も、私の知らないところで、私の知らないルールで、ただ懸命に生きている。私の築いた秩序という防衛線は、彼らにとっては何の意味も持たないのだ。世界は、私の知らない物語で満ちている。それは、穏やかな共存などではなく、私の脆い日常が、常に侵食される危険と隣り合わせだという、ただの事実。
それでも、業務日誌の隅に、私にしかわからない記号で「湖畔、鳥の親子、横断」と書き留めた。あの、分類不能な時間もまた、記録せずにはいられなかったから。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)