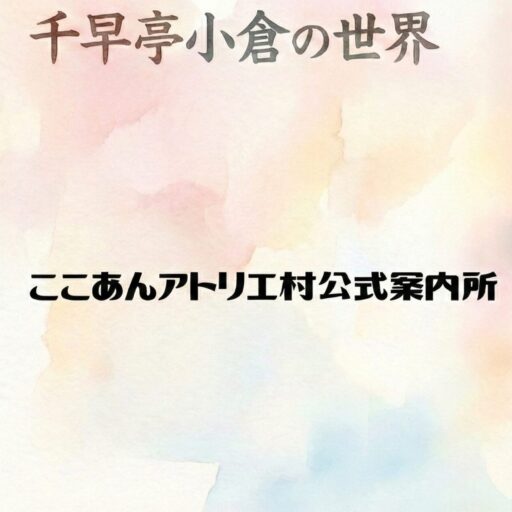これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
休日、少し足を延ばして、湖のほとりのブックカフェ『シズカ』まで来てみた。氷上静さんの選んだ本棚は、うちの図書館とは違う、もっと個人的で、体温のある秩序で満ちている。
カウンターで静さんのパートナー中野小春さんの淹れてくれた珈琲を受け取る。窓際の席に座ったところで、見覚えのある女性に声をかけられた。確か、ボストー区の復興住宅で活動しているボランティア団体の人だ。私とは正反対の、太陽みたいな、屈託のない笑顔を向けてくる。
「あ、図書館の千夏さんですよね?」
「え、はい」
「いつもどうも。今日はお休み?」
当たり障りのない会話が続く。ほとんどは彼女が話しているのだが。彼女の言葉はいつも軽やかで、私の心の防衛線をひらりと飛び越えてくる。その軽やかさが、少しだけ羨ましかった。
やがて、話は自然と彼女が関わっている復興住宅のことに移った。
「そういえば、私が仲良くなったおばあちゃん、最近すごく面白い本を読んでて」
「面白い本、ですか」
面白いとは、なんとも単純な言葉だが、それだけに、どんな本かと心に響く。
「なんていうか、包丁さばきの事典みたいな、すごく専門的な本なんですよ。魚の絵がいっぱい載ってて。あんなマニアックな本、どこで見つけてくるんだろうって思ってて」
その瞬間、私の頭の中の索引カードが、カタカタと音を立てて検索を始める。
『NDC分類:596.2(水産食品・加工)』
『書名:魚類図鑑、あるいは調理法に関する専門書』
『利用者属性:高齢女性』……。
この自動思考は、もはや止められない。
「へぇ、そうなんですね……ん?」
待って。そのキーワードには聞き覚えがある。貸出記録のノートの、インクの染みまで思い出せる。先週、ロマコメ号で貸し出した一冊だ。いつも静かに料理本を眺めている、あの小柄なおばあちゃん。
彼女の穏やかな笑顔。お気に入りだという水色のカーディガン。それを思い出して、私の心が少しあたたかくなる。
「えっ、もしかしてお知り合いですか?」
私の表情が少し緩んだのか、察しのいいボランティアの彼女が「だとしたら、すごい偶然!」と、自分のことのように喜んで、声を弾ませた。
私の完璧な運行計画と貸出記録という、無機質なデータ。彼女が足で稼いだ、個人的で温かい人間関係。その二つが、この村の片隅で、「包丁さばきの事典」という一冊の本を介して偶然につながった。
E・M・フォースターは『ハワーズ・エンド』の中で、「ただ、つなげ」(Only connect…)と書いた。散文と情熱を、手紙と魂を。私がやっているのは、本という物質と、利用者のデータを管理するだけの、乾いた散文的な仕事だと思っていた。でも、その先に、私が直接触れることのない場所で、誰かの日常というささやかな情熱とつながり、こんな温かい物語を生んでいたなんて。
「あのこと」は、あらゆるものを引き裂き、断絶させた。このロマコメ号は、その断絶された世界に、細く脆いけれど確かな一本の糸を渡すための存在なのかもしれない。
(以前の私なら、「運命ですね!」なんて、彼女と一緒にはしゃいでいたかもしれないな……)
内なる私が、少しだけ呆れたように呟く。今の私は、この小さな奇跡を手放しで喜ぶ前に、まず「事例」として記録し、分析しようとしてしまう。それでも、胸の奥がじんわりと温かくなるのを、止めることはできなかった。
「そうだったんですね。……なんだか、嬉しいです」
やっとの思いで絞り出した言葉は、自分でも驚くほど、素直な響きをしていた。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)