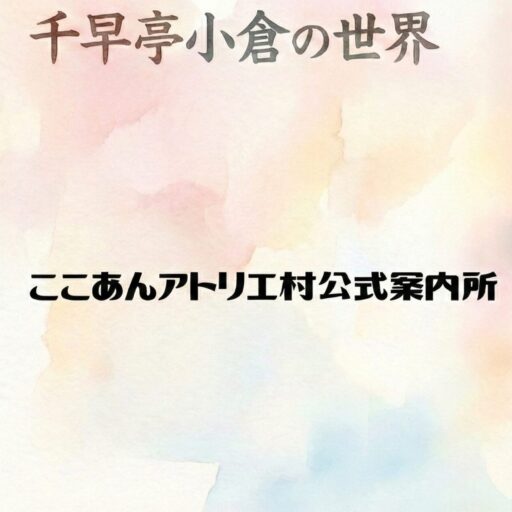これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
ボストー区の仮設団地。ロマコメ号の受付を少し離れ、建物の裏手の、がらんとした広場を漫然と歩いていた。持ち場を離れるなんて規律違反、いつもなら決してしなかっただろう。でも、何かに引かれたのだ。私の完璧な秩序の外側にある、名付けようのない空気に。
そこで、一人の男性を見かけた。私よりずっと年上の、日に焼けた腕をした人だった。地面に座り込み、古い木製の道具……鉋か何かだろうか、その刃をじっと見つめ、手入れをしていた。その赤い、使い込まれた道具箱が、やけに目に焼き付いた。
私の気配に気づいたのか、男性は顔を上げた。気まずさに会釈をすると、彼は作業を続けながら、ぽつり、ぽつりと語り始めた。近くで木工所を営んでいたこと。「あのこと」の日、確定申告の手続きで、たまたま夫婦で役場に出かけていて助かったこと。けれど、湖の近くにあった工房は、機械も、作りかけの家具も、すべて駄目になったこと。数千万円の借金だけが残った、と。
その語り口は、驚くほど淡々としていた。まるで、他人事のように。私の頭の中の索引が、また勝手に動き出す。
『NDC分類:535(木材工芸)』『528(家具工業)』
……いや、違う。この人の言葉は、どの分類棚にも収まらない。これは、生きた歴史そのものだ。
アーネスト・ヘミングウェイの『老人と海』を思い出した。巨大なカジキとたった一人で闘い、全てを失って港に帰ってきた老漁師サンチャゴ。彼は多くを語らない。ただ、そこには敗北では割り切れない、人間の尊厳だけが残る。目の前の男性の姿が、その老人の姿と重なって見えた。彼は、工房の再建に向けて、こうして一つずつ、自分の手で道具を生き返らせている。「こうなったら一発勝負だね」と、彼は何度も繰り返した。その言葉は、悲壮な決意というより、乾いたユーモアさえ滲んでいた。
私がロマコメ号の方を指差して、「あそこで、本をお貸ししているんです」と、かろうじて声を絞り出すと、男性は目元を少しだけ緩めた。 「ああ、息子がさっきから何か読んでるみてえだな」
その一言に、胸を突かれた。 私の仕事は、本を分類し、管理し、貸し出すこと。それは、無機質な作業の連続だと思っていた。でも、その本の向こう側には、こうして、私の知らないところで、誰かの時間が流れている。巨大な無秩序と闘う父親の背中を見ながら、息子さんは、どんな物語を読んでいるのだろう。私の選んだ一冊が、その子の心に、どんな風景を見せているのだろう。
(以前の私なら、「息子さん、どんな本を読んでるんですか」なんて、もっと素直に話しかけられたかもしれないのに…)
心の中で、昔の自分が呆れ顔でささやく。今は、それ以上、言葉を継ぐことができなかった。
活動日誌には書けない。利用者としてカウントされることもない、この数分間。でも、私の心の書棚の、一番大切な場所に、そっと差し込んでおこう。分類は、まだできないままで。
――『老人と海』、再読すること。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)