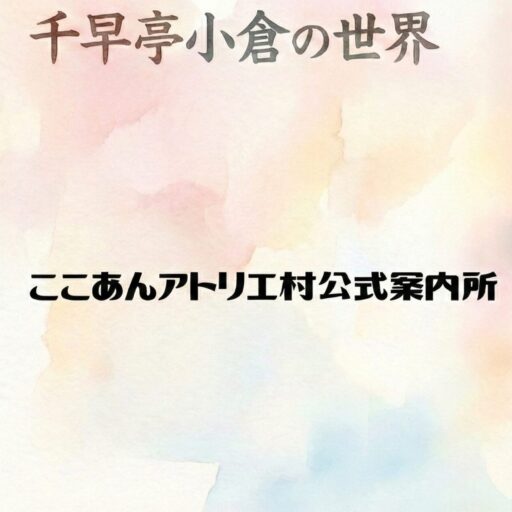これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
図書館の地下駐車場は、機械油と古い紙の匂いが混じり合っている。ロマコメ号の運行準備は、いつだってこの場所から始まる。
「千夏さーん、この絵本、ちょっと角が折れちゃってますけど、補強必要ですかねえ?」
隣でコンテナの中の本を点検していた同僚の鈴木美桜さんが、のんびりとした声を上げる。彼女の周りだけ、いつも空気が数パーセントだけ緩んでいる気がする。私は貸出リストとコンテナの中身を照合しながら、完璧な手順で業務を進める。一冊の抜けもない。分類コードの誤りもない。これが私の防衛線。
その静かな秩序は、穏やかな訪問者たちによって、心地よいさざ波を立てられた。これまで、ここあん村の復興のためにと、たくさんの本を寄贈してくださった出版社の方が数名で視察に見えたのだ。
高島副館長が背筋を伸ばして案内する中、視察者の気配と視線を感じながら、私と美桜さんはいつも通り、黙々と作業を続けていた。そのうちの一人、柔らかな物腰の男性が、私たちのロマコメ号に興味を示したようだった。彼は、車体の側面に並んだ小さな書棚の前に立つと、文庫本の背表紙を愛おしそうに指先でなぞった。
「ああ、この本棚に乗せてもらってる作家の人はうれしいだろうなあ」
それは、独り言のような、けれど確かな重みのある呟きだった。
その瞬間、私の頭の中の索引が自動で動き出す。
『分類:寄贈図書』『ステータス:感謝』と。
しかし、そんな無機質な言葉では、彼の呟きに含まれた温かさを少しも掬い取ることなんてできない。
私は、本を「情報媒体」として見ている。NDC(日本十進分類法)という巨大な宇宙の法則に従って、あるべき場所に収められるべき、静かな星々。けれど、彼の言葉は、その一冊一冊が、誰かの時間と情熱と、そして祈りのようなものが込められた、生きている「手紙」なのだということを思い出させてくれた。
ふと、宮下奈都さんの『羊と鋼の森』が頭をよぎった。ピアノの調律師である主人公が、一台一台のピアノに個性を見出し、森の匂いを感じながら、そのピアノだけが持つ最高の音を探していく物語。作家という人も、きっと同じなのだ。無数の言葉の森を彷徨い、たった一つの最高の響きを探し出す。この小さな書棚に並んでいるのは、ただの紙の束じゃない。そうやって誰かが見つけ出してくれた、たくさんの「音」が詰まっているんだ。
「そうですよねえ、喜んでくれてたら、私たちも嬉しいです」
そう答えたのはもちろん私ではない。美桜さんが、私の心の声を代弁するように、にこにこと笑いながら相槌を打った。私は、ただ頷くことしかできなかった。
(以前の私なら、「美桜さんが書いたわけじゃないでしょ。もちろん、私も書いてないけれど。えへへ」なんて、調子に乗って一緒にはしゃいでいたかもしれないな……)
心の中で、忘れていたはずの自分が囁く。今の私には、この胸に広がった分類不能な温かい感情をどう言葉にしていいのかわからない。
私の仕事は、ただ本を管理し、貸し出すことだと思っていた。でも、違うのかもしれない。作家の想い、それを本という形にした出版社の人の想い、そして、それを待っていてくれる誰かの想い。その目に見えないものを、このロマコメ号に乗せて届けること。それこそが、私の本当の役割なのかもしれない。
業務日報には、この出来事をどう記録すればいいのだろう。「寄贈元関係者来訪、活動に対し好意的な感想あり」と書けばいいのだろうか。そんな乾いた言葉では、あの人の優しい眼差しも、美桜さんの笑顔も、私の胸をよぎったこの温かさも、記録することなんてできない。
この出来事は、まだ分類不能。私の心の書棚に、また一つ、行き場所の決まらない、けれどとても大切な本が差し込まれた。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)