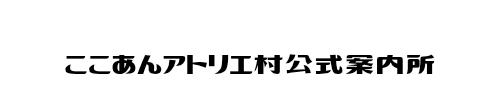ここあん村紹介

そもそも、「ここあん」って?
ちょっと不思議な響きのこの名前。由来には諸説あるのですが、古くから住むお年寄りたちはこう言います。「昔、このあたりには九つの庵があったから、ここあん(九個庵)なんだよ」と。なんだか昔話みたいで、少しロマンチックでしょう?
一方で、新しい住民たちは別の意味を見出しています。「個々のアート(Individual Art)」、略して「ココアト」。それが転じて「ここあん」になったという説。
どちらが正解かは分かりませんが、どちらも正解でいい。古い歴史を大切にする心と、新しい個性を愛する気持ち。その両方が混ざり合っているのが、この村の面白さなのです。
レトロとモダン、そして「森」と「湖」
村の中を歩いてみると、タイムスリップしたような感覚になるかもしれません。 昭和の香りが漂う「克枯地区」では、名画座『夕日座』が今もフィルム映画を回していますし、「小名地区」の商店街では、古いアパートをリノベーションしたアーティストたちが、日々新しい作品を生み出しています。
村の中心には、かつてのランドマーク「ここあんタワー」がそびえ立ち、少し足を伸ばせば、豊かな自然が残る「ここあんの森」や、区境に静かに水をたたえる大きな「湖」が広がっています。
路地裏の古本屋で運命の一冊に出会ったり、移動図書館「ロマコメ号」でコーヒー片手に井戸端会議に参加したり。ここでは、懐かしい風景と新しい発見が、すぐ隣同士にあるのです。
個性あふれる「学びの庭」
この村には、ちょっと変わった……いえ、とても個性的な学生たちも集まっています。 「私立鳥瞰学園ここあん高校」は、村唯一の私立高校。文芸部をはじめ、独自の感性を持った生徒たちが、青春の1ページ(時にはミステリーやコメディのような?)を綴っています。
また、村外には、「私立ここあん大学」の早稲田キャンパスもあります。ここでは、哲学や芸術を深める学生たちが、夜な夜な喫茶店で熱い議論を交わしているとかいないとか。アカデミックな空気が、村に知的な彩りを添えているのも事実です。
「不器用」で「愛すべき」住人たち
そして何より、ここあん村一番の自慢は「人」です。 パン職人、パティシエ、映画館の支配人に、ジャズバーのママ。あるいは、ふらりと現れる作家(ここあん村には、やたら作家がいるという噂も)や、とんでもない発明をしている(かもしれない)研究者たち。
彼らに共通しているのは、自分の「好き」や「仕事」に対して、驚くほど真っ直ぐで、職人気質だということ。ちょっと口が悪かったり、不器用だったりするけれど、困っている人は放っておけない。そんな、人間味あふれる「愛すべき変人」たちが、あちこちで笑ったり、悩んだりしながら暮らしています。
完成された都会のようなスマートさはないけれど、手作りの温かさと、未完成ゆえの面白さが詰まった場所。それが、小古庵アトリエ村、通称「ここあん村」です。
どうぞ、あなただけのお気に入りの路地を、見つけに来てください。
ここあん村の総監督(?)、千早亭小倉について
――ひび割れた箱庭を愛する、ある書き手のこと
この不思議な「ここあん村」の物語を紡ぎ、あるいは拾い集めているのが、千早亭小倉という人物です。
彼とこの村の関係は、少し変わっています。彼はこの村の創造主として君臨しているわけではありません。例えるなら、お気に入りの玩具を並べた「箱庭」を、飽きもせずに眺めている子どものような存在と言えるでしょう。かつて、電車の揺れに身を任せながら国語辞典の例文を読み比べ、そこに無限の世界を見出していた少年がいました。その少年が大人になり、現実世界の隙間にある「愛すべき矛盾」や「うまくいかない人々」のために用意した居場所。それが、この「ここあん村」なのです。
彼は、村人たちの不器用さを決して笑いません。映画館『夕日座』の映写機が時々止まってしまうことも、移動図書館が道を間違えることも、あるいは住人たちが抱える小さな孤独や偏屈さも、すべて「人間らしさ」として愛おしみます。完璧な都市計画よりも、路地裏のひび割れたアスファルトに咲く雑草や、そこに住む人々の「ちぐはぐな会話」にこそ、物語の種を見つける。そんな、ちょっと天邪鬼で、けれど温かな眼差しを持った観察者です。
物語の構造で遊ぶ、思索家としての一面
ここあん村の記録係としての顔のほかに、彼はもう一つの側面を持っています。それは、物語や言葉そのものを玩具にして遊ぶ、批評家としての一面です。「小説はいかにして作られるのか」「読者はどこで感動するのか」といった物語の骨組み(構造)をあえて露わにしたり、架空の評論家に作品を解説させたり。そんなメタフィクション的な仕掛けを用いて、フィクションと現実の境界線を行ったり来たりするような作品も数多く手がけています。それもまた、物事を一つの側面からだけでなく、斜めから、裏から、あるいは「注釈」から眺めてみようとする、彼の尽きせぬ好奇心の表れなのかもしれません。
おそらく今も彼は、村の喫茶店「小古庵」の片隅で、冷めたコーヒーを前に、誰かのとりとめのない言い訳に耳を傾けていることでしょう。「ホントだねぇ」と、面白がりながら。