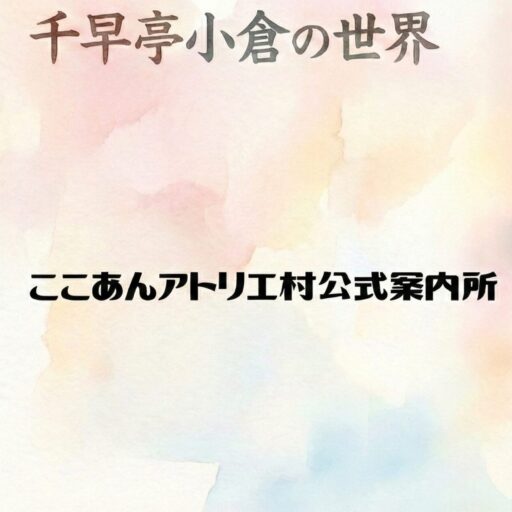これは、日記という名を借りた私の記憶。
某月某日
昨日の地鳴りの残響が、まだ耳の奥で燻っている。日曜の朝。アパートの部屋はしんと静まり返っているのに、体の芯がずっと細かく振動しているような感覚が抜けない。
昨日の午後、ロマコメ号はボストー区の復興住宅前に停まっていた。夏休みに入った子供たちが、返却されたばかりの図鑑をカウンターで広げている、いつも通りの光景。その、はずだった。
ゴゴゴ、という低い音。地面から直接、背骨を突き上げてくるような衝撃。ロマコメ号の車体が、きしんだ音を立てて大きく揺れた。子供たちの小さな悲鳴。私の喉は凍りつき、声が出なかった。視界の端が白んでいく。あの日の記憶――将棋倒しになる書架、舞い上がる粉塵、ホコリの匂いと絶望が混じり合った、あの空気。息が、できない。
「お、揺れるねえ」
「こりゃ4くらいあるかな」
我に返ると、集会所の軒先でお茶を飲んでいたおとうさんたちが、空を見上げながらこともなげに話していた。彼らの顔に恐怖の色はない。長年連れ添った厄介な持病をいなすような、諦めにも似た落ち着き。その声が、パニックの淵から私の腕を掴んで引き戻してくれた。
この光景は、まるでアルベール・カミュの『ペスト』の世界そのものではないか、と思った。ペストという不条理な災厄に閉ざされた街で、人々は次第に恐怖に慣れ、絶望に順応し、それでも日々の務めを淡々とこなしていく。ボストー区の住民たちの強さは、リウー医師が抱えていたあの種の、巨大な不条理と共存せざるを得ない者の諦念に似ている。私は、まだその境地には到底立てない。
巡回を終え、図書館に戻った。開架フロアは何も変わらない。私が毎朝整える書架は、背表紙のライン一本乱れていなかった。完璧な秩序。私の聖域は守られた。そのことに安堵し、深く息を吐く。
異変は、閉架書庫で起きていた。 点検のために薄暗い書庫へ足を踏み入れた瞬間、床に落ちていた白色の棒が目に入った。天井とスチール書架を繋いでいた突っ張り棒が、1本、根本から折れて転がっていた。
それは、ただの棒ではなかった。私の築き上げた完璧な秩序が、いとも容易く壊されることの証明。あの混沌は、私がどれだけ壁を高くしても、鍵をかけても、いつでもすぐそこにいて、こうして脆い部分から侵食してくるのだという、冷たい宣告。
昨夜は、ほとんど眠れなかった。
深夜、棚の奥に隠しておいたファミリーパックのクッキーを、包装を破るのももどかしく、粉々になったものまで口の中に掻き込んだ。甘ったるいバターの香りが、自己嫌悪とない交ぜになってむせそうになる。
秩序を渇望する私が、その実、最も無秩序な行為でしか、己の恐怖を鎮められない。
月曜の朝が来る。折れた突っ張り棒の代わりに、もっと強度の高いものを発注しなくては。 そして、何事もなかったように、ロマコメ号のキーを回すのだ。私の日常という、脆い秩序を守るために。
これは、日記という名を借りた私の記憶。
![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)